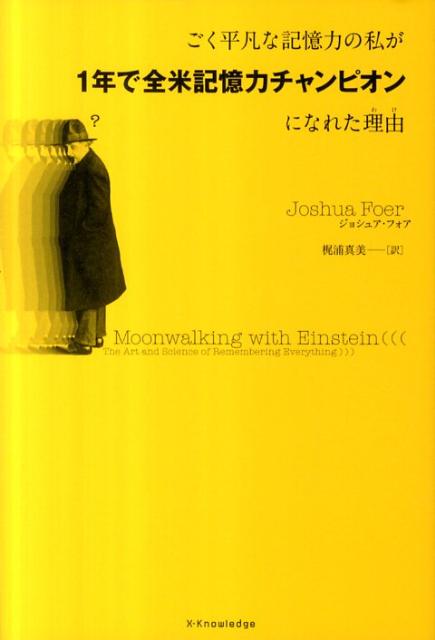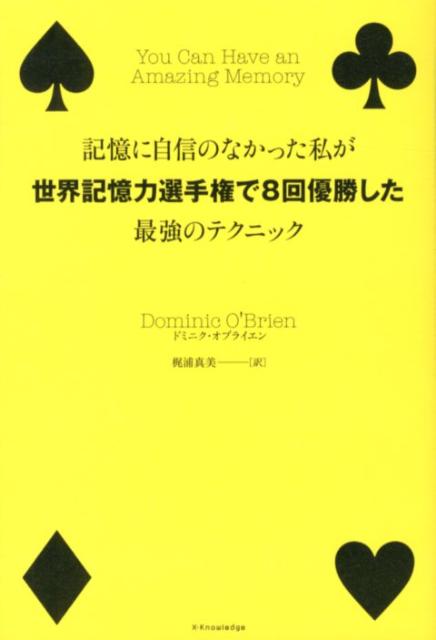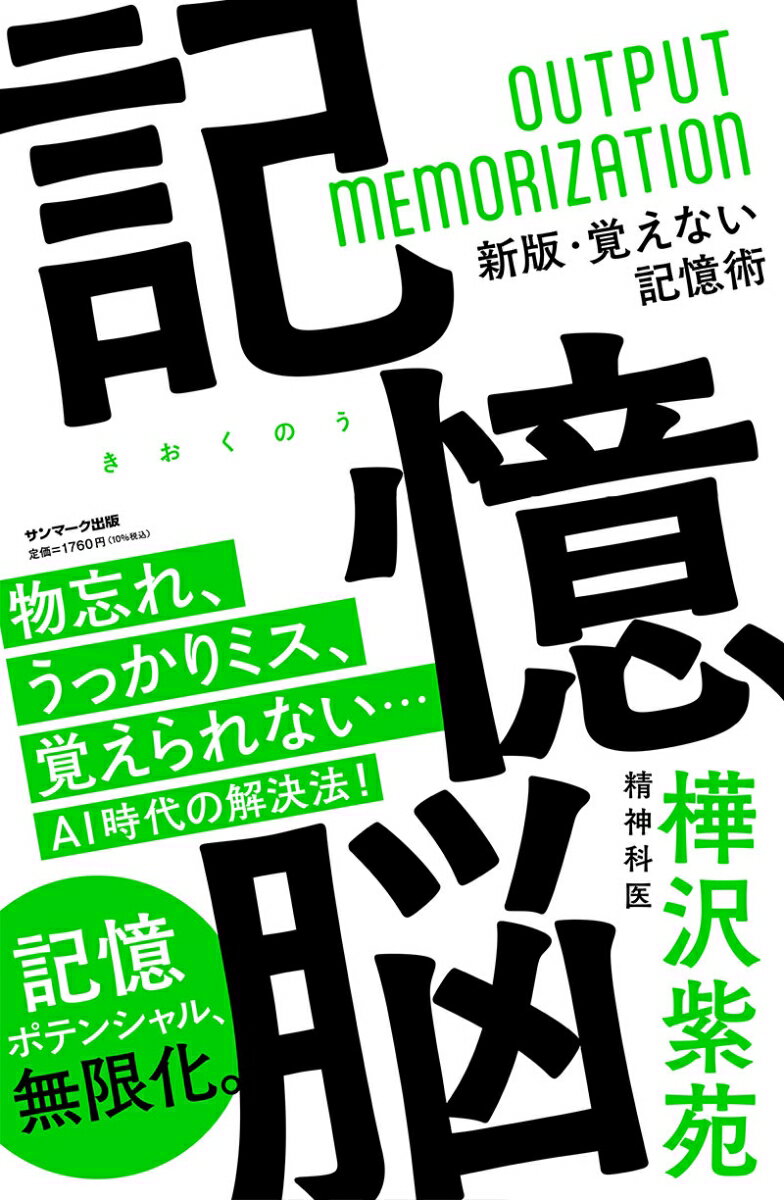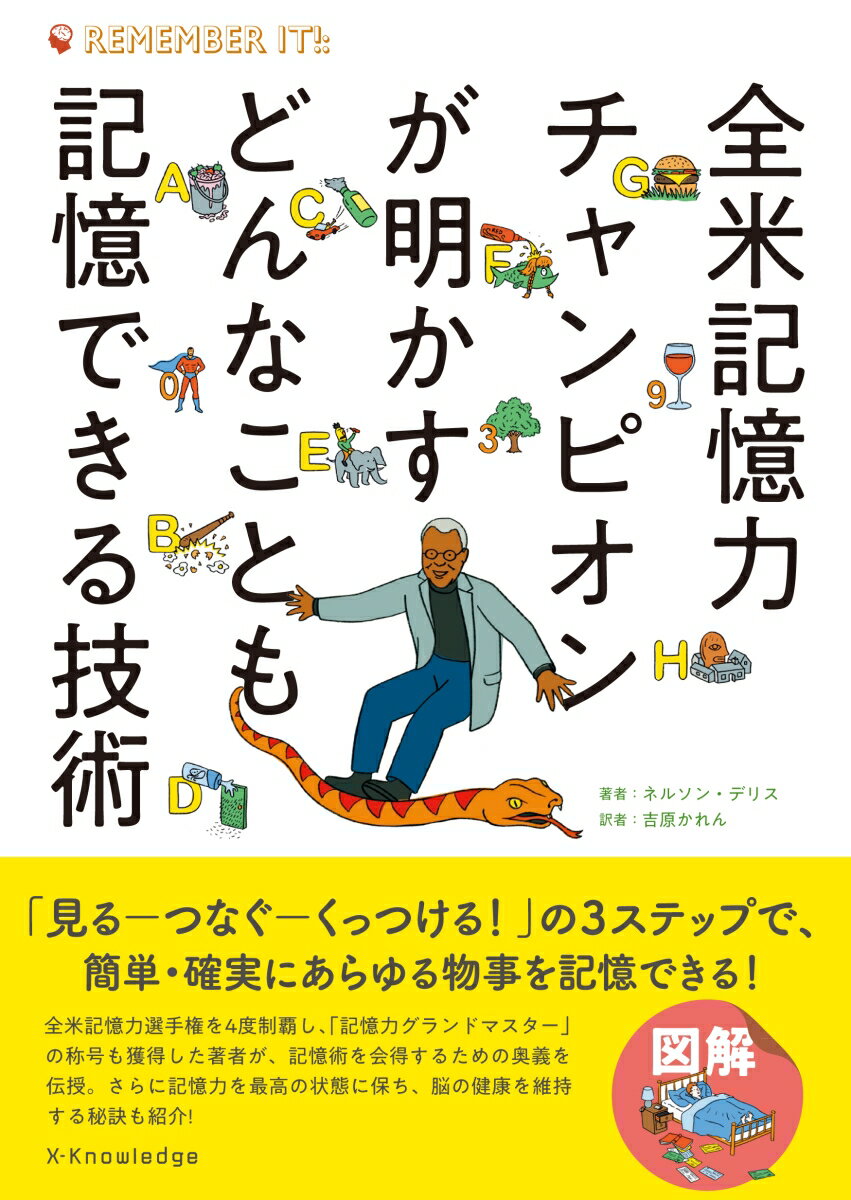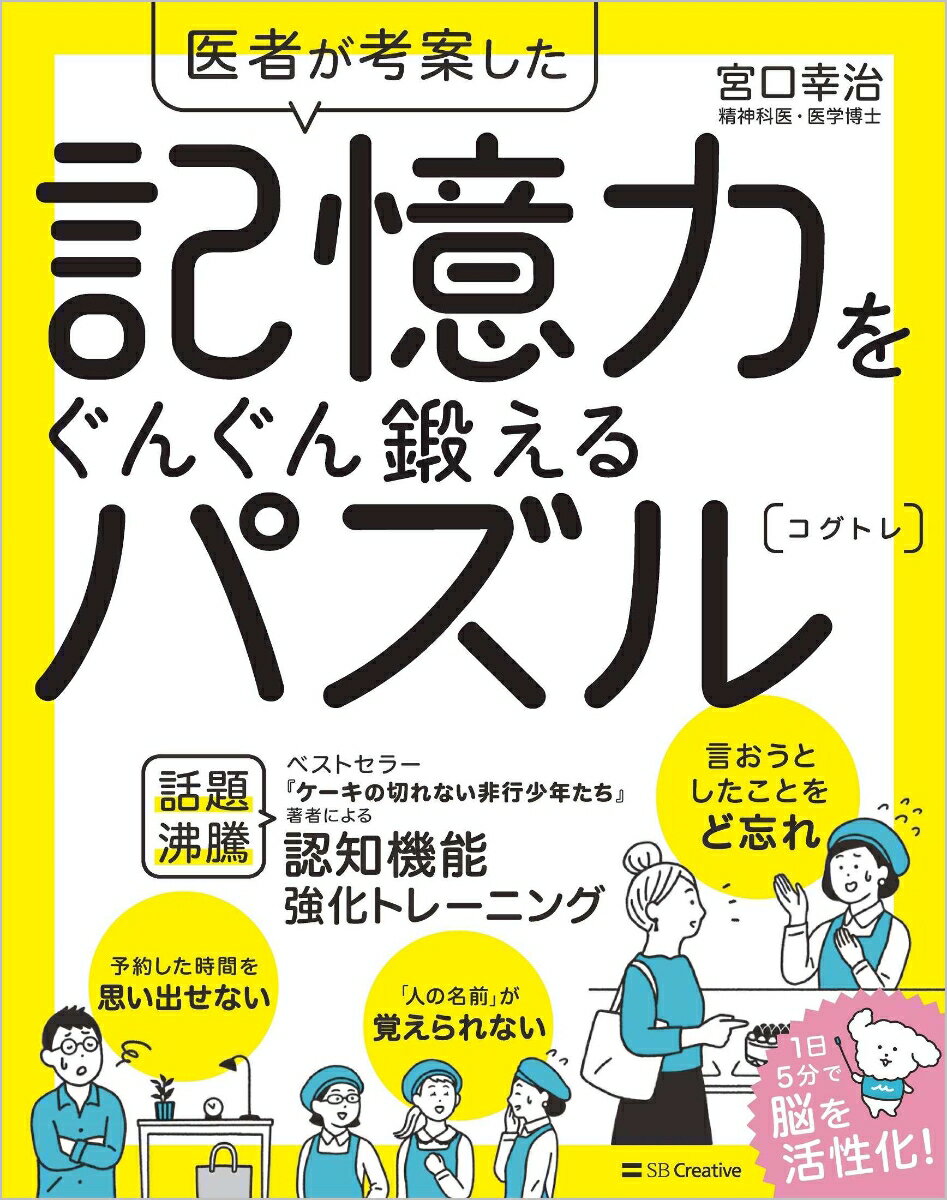2025-04-13
記憶力アップにおすすめの本8選
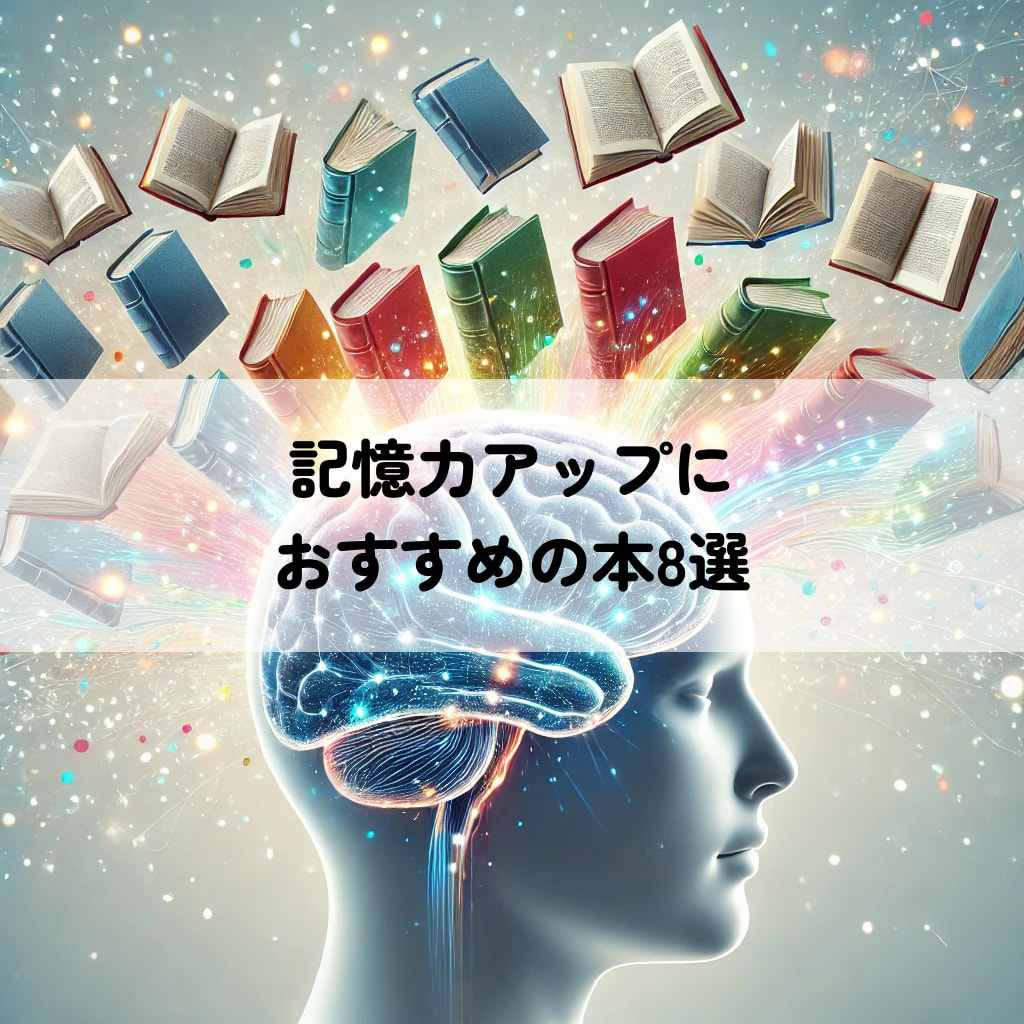
「最近物忘れが増えた気がする…」
「覚えたはずのことをすぐに忘れてしまう…」
そんな記憶力にまつわる悩み、誰でも一度は感じたことがあるのではないでしょうか?
実は、記憶力は生まれつきの才能ではなく、正しい知識と具体的なトレーニングによって誰でも高めることができるスキルの一つです。
今回のブログでは、脳科学・習慣・勉強法など、さまざまな視点から記憶力アップに役立つおすすめの本を8冊ご紹介します。
「覚えるのが苦手」「忘れっぽい」と感じている人は、きっとこの中にあなたにピッタリのヒントがあるはず。
今日から実践できるアイデアが満載の一冊に、ぜひ出会ってみてください。
目次
1日1文読むだけで記憶力が上がる!おとなの音読(加藤 俊徳)
『1日1文読むだけで記憶力が上がる!おとなの音読』(加藤 俊徳 著)は、「たった1日1文読むだけで記憶力が上がる」という、手軽さと効果が両立した脳トレ実践書です。 読んだその日からすぐに実践できる方法がわかり、音読の習慣が脳に良い理由が理解できるのと、 毎日の積み重ねが「記憶力アップ」につながるという実感が得られます。時間がない人でも無理なく始められる脳のトレーニング本です。
こんな人におすすめ
- 最近もの忘れや集中力の低下が気になる人
- 簡単にできる記憶力アップ法を探している人
- 勉強や仕事で「覚える力」を高めたい人
- 忙しくても続けやすい脳トレを探している人
- 脳科学に基づいたトレーニング法に興味がある人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.音読は脳の広い領域を同時に刺激する最強の記憶力トレーニングである
- 読む・聞く・話す・理解するという複数の脳の機能を同時に使うことで、記憶力アップに直結することがわかります。
- 2.脳番地トレーニングという考え方
- 脳には8つの役割(番地)があり、音読はその多くを一度に鍛えることができる、という脳科学的アプローチが学べます。
- 3.毎日1分・1文でも継続が効果を生む
- 難しいことをやらなくても、短時間・少量でもOKという継続重視の考え方が得られます。
この本を読んでできるようになること
- 1.毎日の音読習慣を通じて、記憶力・集中力・理解力が自然と鍛えられる
- 音読するだけで、脳の活性化・記憶の定着・情報処理速度の向上が期待できます。
- 2.誰でも取り入れやすい「1日1文」の実践方法がわかる
- 短くて負担のないトレーニングだから、忙しい人でも無理なく継続できます。
- 3.脳番地を意識したセルフトレーニングの考え方が身につく
- 「読む」「声に出す」「意味を考える」を同時に行うことで、脳を効率よく鍛える習慣が身につきます。
- 4.仕事・勉強・日常生活のパフォーマンス向上につながる
- 記憶力だけでなく、言葉にする力・理解力・集中力のアップによって、日々の行動やアウトプットの質が高まります。
ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力チャンピオンになれた理由(ジョシュア・フォア)
この本は、「記憶力は才能じゃない。誰でも磨ける技術だ」という強烈なメッセージを伝えてくれる1冊です。 記憶力アップの具体的な方法がわかり、記憶=楽しむ・遊ぶ・工夫することだと感じさせてくれます。 読むだけで「記憶の世界」にワクワクできる実践ストーリーと実践的な記憶術を教えてくれます。
こんな人におすすめ
- 記憶力に自信がないけど何とかしたい人
- 効率的な覚え方や記憶術を学びたい人
- 英単語・資格試験・仕事の知識などを覚えたい人
- 暗記が苦手だけど創造力や工夫は得意な人
- モチベーションが上がる記憶の実践ストーリーを読みたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は才能ではなく「鍛えられるスキル」である
- 記憶力の良し悪しは生まれつきではなく、記憶術を正しく使えば誰でも劇的に伸ばせるという発見があります。
- 2.世界の記憶術チャンピオンたちが実践するテクニックは意外とシンプル
- 特別な頭脳ではなく、イメージ力やストーリー化による記憶方法が効果的であるとわかります。
- 3.覚えたいことを「面白く」「印象的」に変換する発想が重要
- 記憶法は単なる暗記ではなく、創造力やユーモアが記憶力アップに大きく影響することに気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.誰でも使える記憶術(メモリーパレス・イメージ変換・語呂合わせなど)の基本がわかる
- 具体的な方法と実践例が紹介されており、自分でもすぐ試せるようになります。
- 2.覚えにくい情報でも「記憶に残る形」に変換する発想が身につく
- 数字・人名・歴史・英単語などをイメージ化・ストーリー化することで、驚くほど記憶しやすくなります。
- 3.記憶トレーニングを習慣にする大切さがわかる
- 1日10分でも続けることで、誰でも記憶力を大きく伸ばせると実感できるようになります。
- 4.記憶力アップは「人生の幅を広げる力」になると気づける
- 記憶力が高まることで、自信・学習効率・人間関係など、日常生活にもポジティブな変化が生まれます。
記憶に自信のなかった私が世界記憶力選手権で8回優勝した最強のテクニック(ドミニク・オブライエン)
『記憶に自信のなかった私が世界記憶力選手権で8回優勝した最強のテクニック』(ドミニク・オブライエン 著)は、ただの記憶法の解説書ではありません。 著者自身の「記憶が苦手だった頃の悩み」から「世界一になるまでの工夫と努力」がリアルに語られており、読むほどに 「記憶は才能ではなく、技術で磨ける」 「覚えることは、もっと面白くて自由でいい」 そんなポジティブな気持ちに変わっていく1冊です。記憶術の本質は「創造力」と「遊び心」。 これまでの「暗記はつらい」というイメージが、きっとガラリと変わるはずです。
こんな人におすすめ
- 記憶力に自信がない人
- 暗記が苦手で悩んでいる人
- 短期間で多くの情報を覚える必要がある学生・ビジネスパーソン
- 世界レベルの記憶術を学んでみたい人
- 覚えることをもっと楽しく・効率的にしたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は生まれつきの能力ではなく「正しい方法」で後天的に伸ばせる
- 世界チャンピオンでも、もともとは普通の人。だからこそ、記憶術は誰にでも効果があるとわかります。
- 2.世界大会で実際に使われた最強の記憶テクニックを学べる
- 多くの記憶術本が紹介する「理論」だけでなく、実際に成果を出した具体的な方法が詳しく書かれています。
- 3.覚えることは「楽しく」「カラフルに」「イメージ豊かに」すると定着する
- 記憶のポイントは「面白い」「変」「五感を使う」など、印象に残る工夫にあると気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.世界基準の記憶術(メモリーパレス、数字変換法、連想法など)が理解できる
- プロの記憶術が初心者にもわかりやすく説明されており、自分で実践できるようになります
- 2.人の名前・数字・英単語・長文など、あらゆる情報を効率よく覚える方法が身につく
- 日常生活やビジネス、勉強で役立つ具体的なシーン別の記憶法が紹介されています。
- 3.覚えたことを長期間忘れにくくする記憶の定着法がわかる
- 「1回覚えて終わり」ではなく、反復と工夫による長期記憶化のテクニックが学べます。
- 4.記憶力を鍛えるトレーニングが楽しく感じられるようになる
- 覚えることが「苦行」ではなく「ゲーム感覚」や「創造的な遊び」になる感覚が得られます。
衰えた脳を呼び覚ます すごい記憶力の鍛え方(加藤 俊徳)
『衰えた脳を呼び覚ます すごい記憶力の鍛え方』(加藤 俊徳 著)は、「年をとったから仕方ない」「物忘れは防げない」とあきらめがちな記憶力の悩みに対して、科学的な裏付けと実践的な解決策を与えてくれる一冊です。 特に印象的なのは、 「脳は年齢よりも“使い方”で変わる」というメッセージ。 毎日のちょっとした行動が、実は記憶力アップの第一歩。 忙しい日常でも無理なく取り入れられる方法が詰まっているので、今日から「脳のメンテナンス習慣」を始めてみたくなる内容です。
こんな人におすすめ
- 最近、物忘れや記憶力の低下が気になっている人
- 年齢による脳の衰えを感じ始めた人
- 脳トレや記憶力アップの具体的な方法を知りたい人
- 毎日続けられる簡単な脳番地トレーニングを探している人
- 仕事・学習・生活のパフォーマンスを高めたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は年齢や衰えに関係なく「鍛え直すことができる」能力である
- 年齢とともに記憶力が落ちるのは自然なこと。でもそれは「回復」や「改善」が可能なことでもあるとわかります。
- 2.鍛えるべきは「記憶力そのもの」ではなく、脳の使い方
- 忘れやすい・思い出せない原因は脳の「使いグセ」にあると理解できます。
- 3.日常生活の中で自然とできる脳番地トレーニングの重要性
- 脳のさまざまな領域(脳番地)をまんべんなく使うことで、記憶力だけでなく思考力・集中力・判断力まで改善できると気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.忘れっぽさや物忘れを改善するための具体的な脳トレーニングがわかる
- 日常のちょっとした行動(歩く・書く・話す・食べる)を活用したトレーニング方法が豊富に紹介されています。
- 2.自分の脳番地のどこが弱っているかをチェックし、効果的に鍛える方法が理解できる
- 視覚・聴覚・思考・記憶・運動など、それぞれの脳の役割に応じた鍛え方がわかります。
- 3.スマホ・便利な道具に頼りすぎない脳の使い方を意識できるようになる
- スマホ・便利な道具に頼りすぎない脳の使い方を意識できるようになる
- 4.衰えた脳を「活性化」し、日常生活のパフォーマンスが向上する
- 記憶だけでなく、判断・集中・発想・感情コントロールといった日常的な脳の働き全般が改善します。
記憶脳(樺沢紫苑)
『記憶脳』(樺沢紫苑 著)の魅力は、「覚える」だけでなく「思い出す」「伝える」「定着させる」までをトータルで考えられるようになる点です。 とくに、インプット偏重の勉強法に疑問を感じていた人や、学んでもすぐ忘れてしまうことに悩んでいた人には、目からウロコの内容が満載。 記憶は「才能」ではなく「使い方と習慣」で伸ばせるもの。 読むことで、記憶に対する考え方そのものがアップデートされる1冊です。
こんな人におすすめ
- 勉強や仕事で覚えることが多くて悩んでいる人
- 記憶力に自信がないと感じている人
- 科学的に正しい学習法・暗記法を知りたい人
- 学んだことをすぐ忘れてしまう人
- 効果的なアウトプット習慣を作りたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 記憶力アップは「脳科学的に正しい方法」で取り組むと誰でも効果が出る
- 勉強や暗記が苦手な人でも、脳のメカニズムに合った方法なら効率的に覚えられることがわかります。
- 2.覚えるだけでは不十分。記憶のカギは「インプット」と「アウトプット」のバランス
- 詰め込み学習ではなく、覚えたことをアウトプットすることで記憶が強化されるという考え方が学べます。
- 3.忘れてしまうのは当たり前。大事なのは「思い出す訓練」
- 忘れることに焦るのではなく、反復やテスト効果によって思い出す力を鍛える重要性に気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 科学的に正しい記憶力アップの方法がわかる
- 睡眠・運動・食事・休息といった生活習慣の見直しから、具体的な学習法・記憶法まで学べます。
- 効果的なアウトプット習慣(話す・書く・教える)の作り方が身につく
- 人に説明する・ノートにまとめる・SNSで発信するなど、記憶が定着しやすい行動がわかります。
- 3.記憶の黄金時間(寝る前・朝起きた直後)の活用法が理解できる
- いつ勉強・復習すると記憶に残りやすいか、脳の働きを活かした時間活用術が身につきます。
- 4.忘れることへのストレスや焦りが減り、自然体で学習できるようになる
- 記憶力に悩む気持ちが楽になり、脳に優しい学び方を実践できるようになります。
読むだけで記憶力が倍増する本(池田 義博)
『読むだけで記憶力が倍増する本』(池田 義博 著)は、勉強や仕事に役立つ記憶術の実践ノウハウがギュッと詰まった一冊です。 とくに印象的なのは、「記憶力が良い人=覚え方が上手い人」という考え方。 単なる根性論ではなく、誰でも再現できるテクニックと実例が豊富なので、 「覚えることへの苦手意識がなくなる」きっかけになるはずです。
覚えることが楽しくなり、「もっと記憶したい」と前向きになれる。そんなポジティブな変化が期待できる実践的な本です。
こんな人におすすめ
- 暗記や記憶が苦手な人
- 効率的にものを覚えたい学生・社会人
- 覚えてもすぐ忘れてしまう人
- 試験勉強や資格取得で大量の情報を覚える必要がある人
- 日常生活の「覚える力」を底上げしたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は「覚え方のコツ」を知るだけで劇的に変わる
- 重要なのはセンスや才能ではなく、記憶のしくみに合った覚え方を知ることだとわかります。
- 2.記憶に残る情報は「印象的」「具体的」「面白い」が共通点
- 情報をそのまま暗記するのではなく、イメージ化やストーリー化などの工夫が大切であることが学べます。
- 3.誰でもすぐに使える記憶術は日常のさまざまな場面で応用できる
- 人の名前・数字・資格試験・英単語など、多様な場面で役立つテクニックが紹介されています。
この本を読んでできるようになること
- 1.自分に合った最適な記憶術を選べるようになる
- 「連想法」「語呂合わせ」「場所法(メモリーパレス)」など様々な技法を学び、シーン別に使い分ける力が身につきます。
- 2.無理に繰り返すのではなく、「1回で覚えやすい工夫」ができるようになる
- 覚えたい内容にイメージ・感情・関連付けを加えるコツが具体的にわかります。
- 3.覚えた情報を「忘れにくくする習慣」を実践できる
- インプットとアウトプットのタイミング、復習のコツなど、記憶定着のポイントが理解できます。
- 4.仕事・勉強・日常生活の記憶力を効果的に高められる
- 名刺・人名・数字・資料・語学など、日常のあらゆる「覚える場面」で成果が実感できるようになります。
全米記憶力チャンピオンが明かすどんなことも記憶できる技術(ネルソン・デリス)
この本の最大の魅力は、著者ネルソン・デリスが「もともとは普通の人」だったということ。 才能や特別な頭脳ではなく、正しい方法と繰り返しの訓練によって世界一の記憶力を手に入れた実体験が、読む人にリアルな説得力を与えてくれます。 ちょっとした「遊び心」や「工夫」を加えるだけで、覚えることが楽しく簡単になる、初心者から上級者まで幅広く使える実践的な 本です。
こんな人におすすめ
- 記憶力に悩んでいるすべての人
- 短時間で効率的に覚える方法を知りたい人
- 世界レベルの記憶術を実践したい人
- 楽しく・遊び感覚で暗記に取り組みたい人
- 人名・数字・語学・スピーチ・資格勉強に役立てたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は生まれつきの能力ではなく「誰でも鍛えられるスキル」である
- 著者自身が、もともとは特別な記憶力を持っていなかったことから、「努力と正しい方法」で記憶力は劇的に伸びることがわかります。
- 2.世界トップレベルの記憶術は意外とシンプルな仕組みで成り立っている
- 難しいテクニックではなく、イメージ化やストーリー化、メモリーパレスなど誰でも実践可能な方法であることが学べます。
- 3.記憶に残す最大のコツは「脳を楽しませること」
- 無味乾燥な情報も、面白く・奇抜に・視覚的に変換することで、脳は覚えやすくなると気づけます。
この本を読んでできるようになること
- 1.全米チャンピオンが使う具体的な記憶術の方法がわかる
- メモリーパレス、連想法、名前・数字の覚え方、長文の暗記 などがステップ形式で紹介されています。
- 2.自分の記憶スタイルに合った覚え方を選べるようになる
- イメージが得意な人、ストーリーが好きな人など、自分に合った記憶術を試しながら学べます。
- 3.日常のあらゆる場面で記憶力を発揮できるようになる
- 人の名前、買い物リスト、英単語、歴史年表、スピーチ、資格試験など、どんな内容でも使える応用力が身につきます。
- 4.「記憶=苦手」という固定観念がなくなる
- 覚えることが「面白い」「ゲーム感覚」で取り組めるようになり、記憶に対するマインドセットが大きく変わります。
医者が考案した 記憶力をぐんぐん鍛えるパズル コグトレ(宮口 幸治)
この本の特徴は、「とにかく楽しく・気軽に・毎日続けられる」という点。 無理に詰め込んで覚えるのではなく、「解く」「考える」「思い出す」 この自然なサイクルを繰り返すことで、知らず知らずのうちに記憶力だけでなく脳全体のパフォーマンスが上がっていく。 そんな実感が得られる、まさに遊ぶように鍛えるための脳トレ本です。
こんな人におすすめ
- 最近、物忘れや記憶力の低下が気になっている人
- パズル感覚で楽しく記憶力を鍛えたい人
- 学校・教育・医療現場のコグトレを自宅でも試したい人
- 子どもから高齢者まで使える脳トレ本を探している人
- 思考力や集中力、注意力も一緒にアップさせたい人
この本が教えてくれる大切なこと
- 1.記憶力は「鍛えることができる筋肉」のようなもの
- トレーニング次第で、誰でも記憶力は高められるという考え方が学べます。
- 2.パズルや簡単な問題を通じて認知機能(コグニション)を強化できる
- 医療や教育の現場でも使われるコグトレの手法は、遊び感覚で脳を活性化できるとわかります。
- 3.記憶力アップに必要なのは「思い出す」トレーニング
- 覚えるだけでなく、思い出す力(再生力)を鍛えることが記憶の定着に直結することを学べます。
この本を読んでできるようになること
- 1.楽しく続けられる記憶力トレーニングが実践できる
- 文章・図形・数字などのさまざまなパズルを解きながら、自然と脳の働きを活性化できます。
- 2.日常生活で役立つ「覚える力」と「思い出す力」の両方が鍛えられる
- 人の名前や予定、数字、場所など、普段の生活で忘れがちな情報がスムーズに記憶できるようになります。
- 3.医療や教育現場で実証されたコグトレの効果を家庭でも体感できる
- 専門家が使う方法を自宅で気軽に実践できるので、老若男女問わず誰でも取り組めます。
- 4.脳のパフォーマンス全体(集中力・注意力・判断力など)も向上する
- 記憶だけでなく、認知機能全般をバランスよく鍛えられるのが特徴です。
最後に
記憶力は、特別な才能ではなく「誰でも鍛えられるスキル」である──。
今回ご紹介した8冊の本には、そんな力強いメッセージと、すぐに実践できる具体的な方法が詰まっています。
音読やパズル、イメージ法、アウトプット習慣など、その手法はさまざまですが、共通しているのは「脳は使い方次第で何歳からでも伸ばせる」という考え方。
「最近、物忘れが増えたかも…」と感じている方も 「もっと効率よく勉強したい!」と思っている方も
まずは気になった1冊を手に取って、今日から記憶力アップへの一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
覚える力が変わると、きっと世界の見え方も変わります。